天理教の鳴物(なりもの)について
鳴物(なりもの)とは「つとめ」に使用される9種類の楽器ことを指します。
男子の鳴物(男鳴物)として、笛、ちゃんぽん、拍子木、太鼓、すり鉦、小鼓。
女子の鳴物(女鳴物)として、琴、三味線、胡弓
が定められています。
「つとめ」とは、親神の人間世界創造の理にもとづいて、「つとめ人衆」が歌に調子をあわせ、九つの鳴物の調べに心を揃え、親神の守護の理を手振りにあらわしてつとめられる「たすけ一条の道」です。
つとめについて詳しは↓をどうぞ
目次
鳴物の歴史
つとめの地歌である「みかぐらうた」は、慶応2年(1866年)から教えはじめられました。
それまでは、拍子木をたたいて、「なむ天理王命」という神名を繰りかえし唱えるだけでした。
教祖(おやさま)は、地歌を教えるとともに、節付け、振り付けをされました。
まず、手振りの教示に力をそそがれ、ついで、鳴物を急きこまれました。
こうした段取りについては、「おふでさき」に記されています。
さらに、
そのうちになりものいれて十九人
かぐらづとめの人ぢうほしいで
(おふでさき第10号27)
や、
やくハりもどふゆう事であるならば
かぐら十人あといなりもの
(おふでさき第10号39)
と記され、鳴物についての9人の役割を明示されています。
具体的には、明治10年(1877年)には、教祖自ら三曲の鳴物を教えられました。
そして、明治13年陰暦8月26日(陽暦9月30日)に、はじめて九つの鳴物を揃えて「おつとめ」がつとめられました。
したがって、この頃までに教祖の教示によって鳴物の設定がなされたと考えられます。
鳴物の教示は、迫害干渉の中でなされたのであり、容易でない中で練習をしなければなりませんでした。
明治21年教会本部設置以降、従来の鳴物のうち、しめ太鼓を台付太鼓(現在使用の様式のもの)に、小鼓を羯鼓(カッコ)に改めました。
鳴物は、官憲の取り締まりの対象ともなりました。
明治29年の内務省の、いわゆる秘密訓令の出たあと、三味線、胡弓などは俗器であり、神前奏楽の鳴物としてふさわしからず、との意見から「おさしづ」をいただいて、やむなく三味線を琵琶に、胡弓を八雲琴に変え、男鳴物の小鼓は羯鼓のままつとめられていましたが、教祖50年祭を迎える旬に元に復したのです。
鳴物の心構え
鳴物は、奏楽の巧拙がかならずしも問題ではありません。
みなが心を一つに合わせ親神の心一つに添って「おてふり」も、地方(じかた)も、鳴物も一つに溶け合い、勇むことこそが、何よりも大切であると教えられています。
男鳴物について
天理教の鳴物「笛」
笛について
笛(ふえ)は気鳴楽器の総称。
狭義には、横笛をさします。
フエは、「吹枝(ふきえ)」の略と考えられ、伝承として「天の鳥笛」「天の磐笛」などの存在が知られているが、実態はわかっていません。
現存最古のものは、正倉院に伝わる竹、石、牙製の4管と言われていますが、近年、天理市の古墳時代後期の築造と推定されている星塚古墳より出土した木片が、松製の笛であることが分かり、年代的に200年も遡るところから注目を集めました。
日本の音楽的な伝統では、神楽に使用される神楽笛、雅楽の唐楽に使用される龍笛、高麗楽に使用される高麗笛、能楽に使用される能管、民間の神楽や祭礼のお囃子などに使用される篠笛などいろいろあります。
これらの笛の構造や、指孔の数に若干の相違がみられるが、材質が主に竹であるのが、アジアのものと共通しています。
天理教で使われている笛
天理教でおつとめの鳴物の一つとして使用しているのは篠笛で、約48cmの長さに歌口と7つの指孔があけられています。
篠笛は、基音のとりかたで12種あり、それぞれ1本、2本と数えます。
天理教で使用しているのは、このうち基音が西洋音楽の「へ」(F)に近い四本調子であす。
九種ある鳴物のうち、定律音の楽器はこの笛だけです。
天理教の鳴物「拍子木」
拍子木(ひょうしぎ)はつとめの鳴物の一つ。
拍子木(ひょうしぎ)について
拍子をとるために打ち鳴らす、方柱形の二つの木からなります。
一般に、古くは「ほうしぎ」ともいい、略して「拍子」とも「木」1ともいいます。
材質は、樫、紫檀、黒檀などの堅いものが好まれます。
歌舞伎や文楽などの芸能では、主に合図や音響効果として用いられ、一打、二打、連打の打ち方があります。
仏になりたての拍子木教では、木魚と同じく誦経の拍子をとるのに用います。
天理教で使われる拍子木
つとめの地歌である「みかぐらうた」の教示がある前は、おつとめは、専ら「なむてんりわうのみこと」の神名を唱えるだけでした。
この時、拍子をとるために拍子木が使用されていました。
嘉永6年(1853)、教祖(おやさま)の末女こかんが浪速にて神名を流した時も、文久3年(1863)、辻忠作が妹くらの病の平癒を願った時もそうであります。
朝夕のおつとめやお願いのっとめでは、拍子木が芯となって一拍ずつ拍子を打つが、その他は男鳴物の一つとして主に二拍に一度、表の拍子(強拍)を打ちます。
おつとめでは、拍子の表裏(強弱)が交替する箇所があり、この時拍子木は、重ね打ちとなります。
天理教の鳴物「ちゃんぽん」
ちゃんぽんについて
ちゃんぽんは金属製体鳴楽器で、インドから教とともに中国を経て伝来した銅鼓(どうばつ)が起源です。
義鎮(にょうばち)、銅拍子とも呼ばれ、主に仏教の儀式音楽で奏されてきました。
これが民間に伝わり、神楽や祭礼の囃子などに広く使用されるようになりました。
呼称も、テビラガネ、テビョウシ、ドビョウシなどと、地域により様々であるが、他にチャッパ、チャッカリコというのがあり、ちゃんぽんの呼称もこれと同じく、打ち鳴らされる音からつけられたものと思われます。
天理教で使われるちゃんぽん
天理教では、おつとめの鳴物の一つとして使用され、拍子木が表の拍子を打つのに対し、裏拍子に打たれています。
天理教の鳴物「太鼓」
太鼓について
太鼓(たいこ)は膜鳴楽器。
主に、中程がすこし膨らんだ木製の箱を胴として、両面に牛や馬の革を張り、特で打ってたらすもの。
革の張り方により、縁を鋲で留める「←打ち太鼓」と、紐で締める「締め太鼓」の2種があります。
天理教での使われる太鼓
おつとめの九つの物の一つ。
当初、締め太鼓を使用していたが、明治21年(1888年)から鋲打ち太鼓のうち、木枠に吊り下げる楽太鼓形式のものを使用するようになりました。
太鼓の使用は、まだ、つとめの地歌の教示のない、神名を唱えるだけの頃に、拍子木と共に用いられていたようです。
『稿本天理教教祖伝」にも、元治元年(1864年)、つとめ場所の上棟式の後、信者達が山中忠七宅に出向いた折、教祖(おやさま)の「神前を通る時には、拝をするように」との仰せにしたがい、大和神社の社前にて、携えていた太鼓などの鳴物を打ち鳴らしました。
これが神職の咎めるところとなり、人々は3日間留め置かれ、太鼓は没収となった(56頁-57頁)とあります。
また、慶応2年(1866年)の秋には、小泉村不動院の山伏がお屋敷にやってきて、刀で神前にあった太鼓を2個引き裂くなどの乱暴を働いた(67-68頁)とあります。
「おふでさき」には
そのところなにもしらざる子共にな
たいことめられこのさねんみよ
(おふでさき第16号54)
と記されています。
天理教の鳴物「すりがね」
すりがねについて
すりがねは型金属製体鳴楽器。
本東周縁部に紐をつけ、左手に下げて、右手に持った撞木で中央や周辺部を打ったり、摺ったり、して鳴らします。
伝来は古く、特定できていません。
各地の祭礼や民間の音楽に広く使用されており、呼称も様々です。
天理教での使われるすりがね
天理教では、おつとめの鳴物の一つすり鉦として使用しています。
ただし、当初手持ちであったが、明治20年代に雅楽の鉦鼓と同じ型のものを使用するようになり、したがって撞木も2本使っています。
奏法としては、雅楽では、中央部のみ打つが、手持ちのときと同じように、中央を摺りおろし、周辺部を打つという違いがあります。
天理教の鳴物「小鼓」
小鼓について
鼓は、インド起源の楽器で、日本には6、7世紀頃に伝来しました。
平安末期には、左手で調緒を握り、右手で打つ奏法が考え出され、その小振りのものを小鼓と呼ぶようになりました。
桜の木で胴を作り、両面を皮張りの輪で挟み、調緒でとめます。
左手の調緒を握る加減と、右手の打つ強弱で、種々の音を出します。
能や歌舞伎を初め、民間の各種の芸能にも広く使用されてきました。
天理教で使われる小鼓
天理教では、おつとめの鳴物の一つとして使用しています。
明治21年(1888年)頃より昭和11年(1936)の教祖50年祭まで、小鼓の代わりに羯鼓を用いたことがあります。
三曲(女鳴物)について
三曲とは
三曲(さんきょく)とは、九つの鳴物(なりもの、楽器)のうち、琴、三味線、胡弓の女子の鳴物をさしていいます。
教祖(おやさま)は、慶応年間から、つとめの地歌である「みかぐらうた」を示され、手振りを、ついで鳴物を教えられました。
迫害干渉がはげしくなってくる明治10年(1877年)には、年のはじめから、教祖自ら三曲の鳴物を教えられました。
最初に教えられたのは、琴は辻とめぎく(当時8歳)、三味線は飯降(のち永尾)よしえ(当時12歳)、胡弓は上田ナライト(当時15歳)、控えは増井とみ、(当時11歳)でした。
この辺の事情については、「おさしづ」では、
「その後(のち)もう一つ鳴物三人、一人は控え。どうしたらよかろうか、師匠というか、まあそこえ/\稽古さして始め掛けた。元々容易やない。紋型無い処、何っから師匠出来て、手を付けたと言うやない。一を抑え、三を抑え、手を付けさした。」(おさしづ明治31年5月12)
といわれているが、当時直接に教えていただいた永尾よゑによれば、教祖は、
「習ひにやるのでもなければ教へに来て貰ふのでもないで、このやしきから教へ出すものばかりや、せかいから教へて貰ふものは何もない、このやしきから教へ出すので理があるのや」(「水尾芳枝母口述記」「復元』第3号)
といわれ、手をつけられたといいます。
このとき、三曲を習ったのは、当時10歳前後の幼い人々であり、これらの人々を対象にしての教示であったことに、注意をはらう必要があります。
こうして、明治13年陰暦8年26日、はじめて三曲をふくむ鳴物全部を揃えて、「おつとめ」がつとめられたのです。
これが、明治29年4月内務省のいわゆる秘密訓令が出たあと、三味線を琵琶に、胡弓を八雲琴にやむなく改められました。
訓令後の大阪府令には、教会などでの停止条項に「祭典仏事等ヲ行フニ際シ、猥雑ナル遊器(三味線、胡弓)ノ類ヲ用フル事」をあげています。
それ以前にも「内務省より鳴物の内三味線入れるのを喧しく言う」(おさしづ明治28年4月19割書)
ということがあったようであるが、明治29年5月20日には「鳴物は男ばかりにて、女の分は改器なるまで当分見合わせ度く願」とか、30年11月20日には「九つ鳴物の内、三味線を今回薩摩琵琶をかたどりて拵えたに付御許し願」、さらに同日に「胡弓の事願」という「おさしづ」を願っています。
それに対して、
「後々の事情は詳しいさしづするから、鳴物一条は許そ/\。皆寄り合うて、喜ぶ心を以てすれば、神は十分守護するとさしづして置く。鳴物は許そ/\」(おさしづ明治30年11月20日)
と指図されています。
このあと明治34年頃まで、女物についての指図がみられます(おさしづ明治31年3月26日、明治31年5月12日参照)。
そこで、教祖から直接教えられたとおりの三曲の稽古が促されたようです(おさしづ31年11月26日参照)。
その後、改器された鳴物は、教祖50年祭の昭和11年(1936年)1月26日に元に復しました。
なお、叩き打って拍子をとる男子の鳴物が、固定音律の楽器であるのに対し、女の大山は、不定音律のものでいり、どんな調子にも合わすことができるものです。
天理教の鳴物「三味線」
三味線について
三味線(しゃみせん)とはリュート型笠間久部の名称から、中国の琵琶を起源とする説もあるが、フレットがないところから胡弓との折衷とみた方がよく、形態的には、琉球音楽の三線を起源とする方が理に適っています。
やや外側に丸みの帯びたなどを材料にした四角の胴に、両面、描きれは犬の皮を張り、1m弱の同材の棹をさし込み、銀製の3本の糸を渡して駒で受け、左手指で勘所を押さえ、撥で弦を弾いて音を出します。
天理教で使われる三味線
三味線天理教では、おつとめの鳴物の一つとして使用され、調弦は、一の糸と二の糸が完全5度、二の糸とこの糸が完全4度となる二上りを用いています。
教祖は、明治10年(1877年)に三曲の鳴物を教示されました。
三味線については、飯降よしゑ(後の永尾)に「よっしゃんえ(飯降よしゑのこと)、三味線の糸、三、二、と弾いてみ、ひとーつと鳴るやろが。そうして、稽するのや」などと、3年間直接教えられました。(「稿本教祖伝逸話篇」第53、54話参照)。
おさしづにも、
「紋型無い処、何っから師匠出来て、手を付けたと言うやない。一を抑え、二三を抑え、手を付けさした。」(おさしづ明治31年5月12日夜)
とあります。
明治29年の内務省訓令により、俗楽器を神前で奏するのは相応しくないとの意見により、昭和11年(1936年)の教祖50年祭前まで、薩摩琵琶を三味線に代えて使用しました。
天理教の鳴物「琴」
琴について
琴ことは広義には、弦楽器の総称です。
本来、柱のある「そう(箏)のこと」と、柱がなくかんどころを押さえて奏する「きん(琴)のこと」の区別があります。
「琴」の漢字を当てて「箏」を意味する江戸時代の誤用が、今日も行われています。
天理教で使われる琴
天理教では、おつとめの鳴物の一つとして、13弦で柱のある等のことが使用されています。
琴は東アジア一帯に分布しており、楽器分類学上から長胴ツィター型弦鳴楽器です。
日本へは、中国の宴饗楽で使用されていたものが、奈良時代に伝来したものと考えられています。
調弦は俗楽の平調子であるが、左手奏法である押しいろの位置からすると、雅楽の平調に相当します。
爪は、生田流の長方形の爪が用いられています。
天理教の鳴物「胡弓」
胡弓について
胡弓(こきゅう)は広義には、アジア地域の擦弦楽器の総称。
日本では、主に三味線を小型にしたもので、馬の尾を束ねた弓を用いて奏する楽器をいい、その起源については、三味線改良説、中国系胡琴の改良説など諸説があり、未だ定説がありません。
江戸初期にはすでに現在の形になっていました。
箏、三味線と共に、三曲合奏として使用されたり、独奏楽器としても用いられています。
西日本には、盆踊りや祭礼のお囃子の一つとして演奏されているところもあります。
天理教で使われる胡弓
天理教では、三下りと二上りの二種があるが、天理教では 二上りを用いている。教祖(おやさま)は、明治10年 (1877年)に三曲の鳴物を教示されました。
胡弓については、 上田ナライトが、身体が揺れ動いて止まらないようになったので、教祖に伺うと、「胡弓、胡弓」と仰せになったので、「はい」とお受けすると身体の揺れも治まり、それからつとめの胡弓を習ったとの伝承があります。(「稿本天理教教祖伝逸話篇』第55話)
明治29年の内務省訓令により、神前で俗楽器の使用は応しくないとの意見により、代わりに八雲琴を使用したが、昭和11年の教祖50年祭のおり復元しました。

 お気に入りに追加
お気に入りに追加 



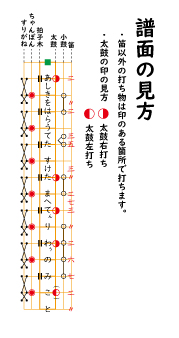




に行こう!2025年イベント情報をお届け!.jpg)
