おさづけの不思議
おさづけの不思議 タイ在住 野口 信也 私は結婚して3年後、タイの大学院で学ぶため、三度目の渡泰をしました。その時も、以前と同じように病気の方の平癒を願う「おさづけ」を取り次ぐため、病気の方のお宅や病院を訪れていました。特にがんや脳腫瘍など、命に関わる病気の方の所へは毎日通っていたので、大学で講義を受けた後、3~4カ所は行く所がありました。 毎日大渋滞が起こるタイには、日本にはないバイクタクシーというものがあります。渋滞をすり抜けて走ってくれるので、4~5時間かかるところを1~2時間程度で移動することができ、たいへん重宝していました。 タイでの最初の2年間、大学へ入って3年半、そして大学院の時と、こうしたことを6年近くも続けていると、時には全く知らない方から「病人がいるので来てもらえないか」という電話がかかってくることもありました。人口およそ600万人を擁するバンコクであっても、少しずつでも続けることで、知らぬ間に色々なつながりができるのだなと感じました。 大学院を修了する少し前のことです。大学の頃からの友人K君から、「お付き合いしている彼女の祖母が危篤の状態だ。おそらく葬儀が明日から一週間行われるので参列してほしい。このおばあさんには、何とか自分たちの結婚式に出席してもらいたいと思っていたけど…」と電話が入りました。 このおばあさんは99歳で入退院を何度も繰り返していて、いよいよなので親族を呼ぶよう医師に言われたそうです。まだご存命ということなので、私はすぐ病院にかけつけ、最後となるであろうおさづけをさせてもらいました。 すると、その夜K君から、明日の葬儀は中止でおばあさんは自宅療養することになったとの連絡が。翌日から帰国するまで、毎日おばあさんのおさづけに通い、K君と孫の結婚式にも出席してもらうことができました。 その後、日本に帰国してから7年ほど経った冬に、タイから一本の電話が入りました。K君からで、彼の義理の姉が良性腫瘍の摘出のため開腹手術をしたところ、悪性腫瘍で腹部全体が侵されていて、卵巣を取るなどできる限りの処置をしたが、もう手の施しようがないとのこと。医師からは「あと3カ月、長くても半年です」と宣告されたそうです。 病人さんのご主人が電話に出られ、「私たち夫婦と娘一人、いつまでも仲良く暮らしていきたい、何とか救けて下さい」と言われました。 ご主人は以前のおばあさんのおたすけのことを知っておられ、真っ先に天理教の神様にたすけを求めてこられたようですが、私はそういう切羽詰まった場面にとても弱く、どうしたら良いか焦っていました。 それでもおさづけをさせてもらうしかないと思い直し、勤務先である天理教海外部の上司に3日間だけ休暇をお願いすると、「人をたすけるためなら何日でも構わない」と許可を下さったので、すぐタイへ出発しました。 飛行機の中で、ふと『教祖伝逸話篇』に書かれている、当時の最も丁寧だと思われる病気平癒の方法を思い出しました。「座りづとめ」と「十二下りのてをどり」を一座とし、一日に昼三座、夜三座、これを三日間行う方法です。 以前、海外の学生がその逸話篇を呼んで、一日6回のおつとめを実際にやってみようと試みたことがありました。私がタイへ到着するのが朝の5時で、帰るのは二日後の夜中の12時ですから、ちょうど丸三日間。よし、これで行こうと決めました。 空港へ到着し、その足で友人宅へ行き一度目のおさづけ。その後すぐバスで一時間半かけて神様を祀っているタイ出張所へ。そこで一回目の座りづとめと十二下りのてをどり。所要時間は約一時間。その後また友人宅へ戻り、病人さんに二度目のおさづけ。そしてまたタイ出張所へ行き、二回目の「座りづとめと十二下りのてをどり」。こうして3回、4回と繰り返しました。 さらに、夜から朝にかけての時間は病人さんのいるお宅へ泊めてもらい、その一室で5回目、6回目をつとめました。これを三日間、6回、6回、6回と繰り返しつとめ、三日目の夜中過ぎに挨拶もそこそこに帰国。おたすけ三昧の三日間でした。それでもまだ確信が持てずに心配で仕方がありませんでした。 年が明け正月、おぢばである先生がこんなおたすけ体験を語ってくれました。 「三日間のお願いづとめはすごいね。ある信者さんが、がんを患って脳まで転移して意識もない状態だった。普通に考えると、ちょっともうたすからないかな、という症状だったけれど、三日間おさづけをさせて頂いたら、少しずつ良くなって、その後の月次祭には付き添いの方と参拝に来られたんだ。翌月の月次祭にはおつとめの奉仕をしてくださったよ」。 私はそこで初めて、自分勝手に悩んでいたことに気が付きました。「そうだ、神様がおられるんだ」と思えた瞬間、不安が一気に消し飛んで、絶対にたすけていただける。そういう気持ちになりました。 3カ月後、再びタイに戻ると、そのがんの女性から「一緒にご飯を食べに行きましょう」と電話がありました。「抗がん剤治療の最中のはずなのに」と思いながらお会いすると、とても元気でした。さらにその1年後には、今度は自分で車を運転して食事に連れて行って下さいました。 抗がん剤治療で抜けていた髪も全部生えそろい、「検査をしてもがんの痕跡が一つもないと、医者が驚いています」と、嬉しそうに話をしてくれました。 たん/\と神の心とゆうものわ ふしぎあらハしたすけせきこむ (三 104) 人間の親である親神様は、不思議な守護を現わし、神の存在をはっきりと認識させ、人々が互いにたすけ合う「人類が本当にたすかる道」へと導いて下さるのです。 彼女はこうして不思議なご守護を頂戴し、家族共々いよいよ人をたすけるための「おさづけの理」を頂戴するためにおぢばがえりを決心しましたが、出発の一カ月前にがんが再発しました。しかし本人も家族も、「早く分かって良かった」と喜び、私がおさづけを取り次ぎに自宅へうかがうと、家族揃っておつとめをつとめ、彼女の平癒をお願いして下さいました。 一家揃って信仰を深める、本当の幸せへの大きな一歩となったのです。 こころの錦 天理教教祖・中山みき様「おやさま」は、朝夕に唱える「みかぐらうた」の中で、こう教えられています。 九ツ このたびまでハいちれつに やまひのもとハしれなんだ 十ド このたびあらはれた やまひのもとハこゝろから 教祖がこのように教えられるまで、人々を悩ませる病の原因は何なのか、はっきりと知る者はいなかったのです。人のことを顧みずに我が身のことばかり考える、その勝手気ままな心遣いこそが病の元であり、その心の色を変えずしてご守護頂くことはできません。 この信仰は、どこまで行っても自分自身の心を立て替えることが第一であり、見た目をよくするために着飾ろうという考えなどは、どこか遠くへ追いやらなければならないでしょう。 教祖は、「外の錦より心の錦、心の錦は神の望み。飾りは一つも要らん」と仰せられ、さらに「もう着るもの無けにゃ、もう無うても構わん/\。美しい物着たいと思う心がころりと違う」と、お諭し下さいます。(M35・7・20) 明治七年、増井りんさんは、目の見えないところをすっきりご守護頂き、この道の信仰につきました。明治十年頃より、十日交代でお屋敷につとめるようになったりんさんは、早朝から夜遅くまで、人の嫌がる便所掃除やニワトリの世話など、どんなことでも喜び勇んで働きました。そして、寸暇を惜しんでは、人だすけの上に苦労を重ねました。 その真実の働きにより、教祖のお守役をつとめるようになったりんさんは、後にこのように語っています。 「人は顔容姿粧ろうよりも、心の磨きが肝心であります。(中略)まず顔容姿粧ろう人は、どうしても心の磨きが足りませぬ。それよりも、心の磨きがまず肝心であります。身にどんな立派な着物を着、立派なものをつけておろうが、心遣いが間違っておったなら、神様の御守護は頂けませぬ。 表面の飾りよりも心の磨き、心の錦が肝要であります。たとえ着物は木綿を着ておろうとも、心遣いが天の理に叶っておりさえしますれば、神様の御守護は結構に頂けます」 (終)



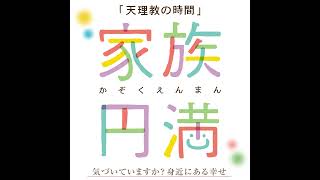


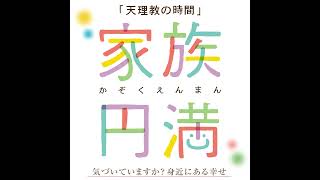
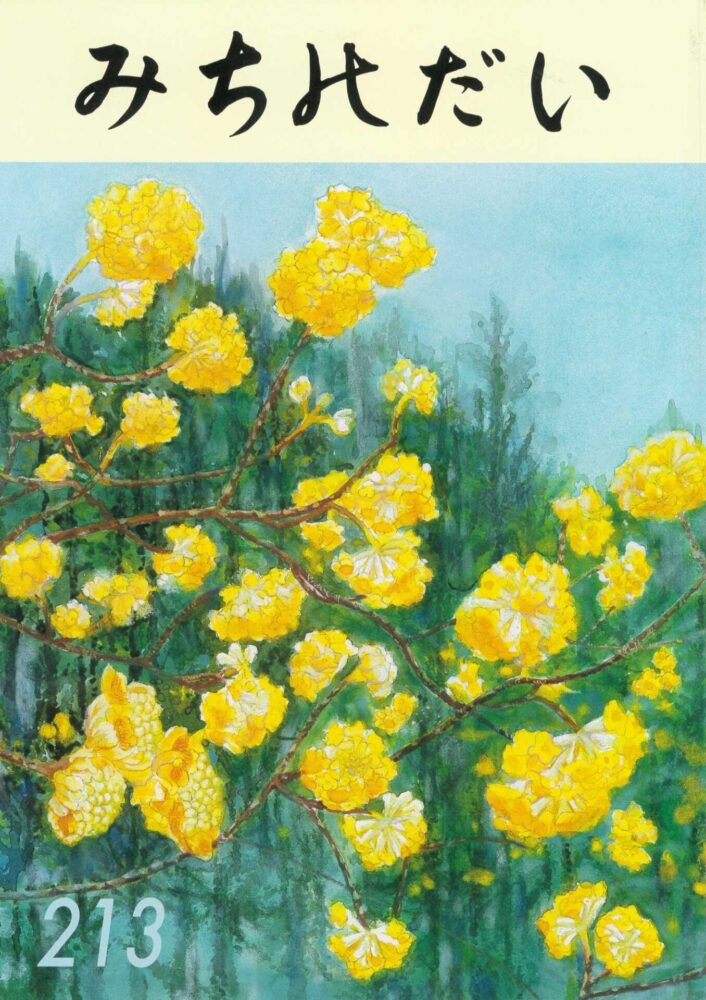


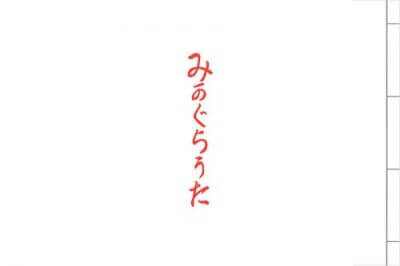
に行こう!2025年イベント情報をお届け!.jpg)
