教祖の教え方は全人類のお手本?【教典第一章 part3】【天理教の教え】
前回の動画では、「月日のやしろ」と「ひながたの親」という教祖のお立場をご紹介いたしましたが、今回は、教祖が「ひながたの親」として、具体的に、どのように私たち人間をお導きくださったのかということについてお話しています。 0:00 オープニング 0:18 おふでさき 4:35 三原典 5:45 例えを用いて導かれた 10:34 終了画面 #天理教の教え#天理教#宗教 二六 麻と絹と木綿の話 明治五年、教祖が、松尾の家に御滞在中のことである。お居間へ朝の御挨拶に伺うた市兵衞、ハルの夫婦に、教祖は、 「あんた達二人とも、わしの前へ来る時は、いつも羽織を着ているが、今日からは、普段着のままにしなされ。その方が、あんた達も気楽でええやろ。」 と、仰せになり、二人が恐縮して頭を下げると、 「今日は、麻と絹と木綿の話をしよう。」 と、仰せになって、 「麻はなあ、夏に着たら風通しがようて、肌につかんし、これ程涼しゅうてええものはないやろ。が、冬は寒うて着られん。夏だけのものや。三年も着ると色が来る。色が来てしもたら、値打ちはそれまでや。濃い色に染め直しても、色むらが出る。そうなったら、反故と一しょや。 絹は、羽織にしても着物にしても、上品でええなあ。買う時は高いけど、誰でも皆、ほしいもんや。でも、絹のような人になったら、あかんで。新しい間はええけど、一寸古うなったら、どうにもならん。 そこへいくと、木綿は、どんな人でも使うている、ありきたりのものやが、これ程重宝で、使い道の広いものはない。冬は暖かいし、夏は、汗をかいても、よう吸い取る。よごれたら、何遍でも洗濯が出来る。色があせたり、古うなって着られんようになったら、おしめにでも、雑巾にでも、わらじにでもなる。形がのうなるところまで使えるのが、木綿や。木綿のような心の人を、神様は、お望みになっているのやで。」 と、お仕込み下された。以後、市兵衞夫婦は、心に木綿の二字を刻み込み、生涯、木綿以外のものは身につけなかった、という。 四五 心の皺を 教祖は、一枚の紙も、反故やからとて粗末になさらず、おひねりの紙なども、丁寧に皺を伸ばして、座布団の下に敷いて、御用にお使いなされた。お話に、 「皺だらけになった紙を、そのまま置けば、落とし紙か鼻紙にするより仕様ないで。これを丁寧に皺を伸ばして置いたなら、何んなりとも使われる。落とし紙や鼻紙になったら、もう一度引き上げることは出来ぬやろ。 人のたすけもこの理やで。心の皺を、話の理で伸ばしてやるのやで。心も、皺だらけになったら、落とし紙のようなものやろ。そこを、落とさずに救けるが、この道の理やで。」 と、お聞かせ下された。 ある時、増井りんが、お側に来て、「お手許のおふでさきを写さして頂きたい。」 とお願いすると、 「紙があるかえ。」 と、お尋ね下されたので、「丹波市へ行て買うて参ります。」 と申し上げたところ、 「そんな事していては遅うなるから、わしが括ってあげよう。」 と、仰せられ、座布団の下から紙を出し、大きい小さいを構わず、墨のつかぬ紙をよりぬき、御自身でお綴じ下されて、 「さあ、わしが読んでやるから、これへお書きよ。」 とて、お読み下された。りんは、筆を執って書かせて頂いたが、これは、おふでさき第四号で、今も大小不揃いの紙でお綴じ下されたまま保存させて頂いている、という。 一七一 宝の山 教祖のお話に、 「大きな河に、橋杭のない橋がある。その橋を渡って行けば、宝の山に上ぼって、結構なものを頂くことが出来る。けれども、途中まで行くと、橋杭がないから揺れる。そのために、中途からかえるから、宝を頂けぬ。けれども、そこを一生懸命で、落ちないように渡って行くと、宝の山がある。山の頂上に上ぼれば、結構なものを頂けるが、途中でけわしい所があると、そこからかえるから、宝が頂けないのやで。」 と、お聞かせ下された。 一七八 身上がもとや 教祖の仰せに、 「命あっての物種と言うてある。身上がもとや。金銭は二の切りや。今、火事やと言うたら、出せるだけは出しもしようが、身上の焼けるのも構わず出す人は、ありゃせん。大水やと言うても、その通り。盗人が入っても、命が大事やから、惜しいと思う金でも、皆出してやりますやろ。 悩むところも、同じ事や。早く、二の切りを惜しまずに施しして、身上を救からにゃならん。それに、惜しい心が強いというは、ちょうど、焼け死ぬのもいとわず、金を出しているようなものや。惜しいと思う金銭・宝残りて、身を捨てる。これ、心通りやろ。そこで、二の切りを以て身の難救かったら、これが、大難小難という理やで。よう聞き分けよ。」 と。これは、喜多治郎吉によって語り伝えられた、お諭しである。 註 二の切り 切りとは、義太夫などに於て、真打が勤める最も格式の高い部分を言う。したがって、二の切りとは、一番にではなくて、二番目に大切なもの、という意。(新村出「広辞苑」平凡社「世界大百科辞典」) ★天理教濃飛分教会は、岐阜県岐阜市にある天理教の教会です。 当教会では、ホームページやTwitterで悩み相談を受け付けています。詳細は下記のホームページ、または、Twitterのプロフィールをご確認ください。 【ホームページ】https://nohhi.org/consultation/ 【Twitter】https://twitter.com/tenrikyonohhi 【Facebookページ】https://www.facebook.com/nohhi.org ★このチャンネルでは、天理教の教えや活動について、分かりやすく説明する動画を配信していきます。 天理教についての疑問や質問などありましたら、メッセージを送ってください。動画作成の参考にさせていただきます。 ★プロフィール 1979年生まれ 岐阜県出身 天理教濃飛分教会の会長の孫として生まれ、高校まで教会で生活する。 天理大学国際文化学部英米学科を卒業後、在外公館派遣員として在南アフリカ共和国日本国大使館にて勤務。 25歳から天理教校本科にて、天理教学を学ぶ。 27歳から天理教教会本部にて勤務。うち約5年間は天理教アメリカ伝道庁(ロサンゼルス)にて書記として勤務。 36歳の時、天理教教会本部の勤めを終え、天理教濃飛分教会に戻る。 40歳で天理教濃飛分教会の会長に就任。 天理教の教会長としてのつとめの他、養育里親、イライラしない子育て講座講師( TFA)、地域の見守り、水防団員などとしても活動をしている。 ★関連動画 天理教の教え関連 「青年会本部 一月例会 青年会長夢プレゼン」https://youtu.be/nEMumfpyKdQ 「第1遍 「すべて心通りに現れてくる」」https://youtu.be/icj0PsYMeyk 「2021年から時代はこう変わる」https://youtu.be/EKgRCAR8_Po 「天理教の勧誘が来たので天理教について解説したくなりました」https://youtu.be/m7fkTOzaifg 「信者数日本2位のマンモス宗教。天理教の総本山・天理市にいったら、何もかもが想像以上だった」https://youtu.be/FtEtEgKPh6k 「天理教講話 筒井敬一 おやさと講演会アーカイブtenrikyo」https://youtu.be/vJHJcpZWdx8 「天理教教祖と松本人志」https://youtu.be/WSVu5MXCVM8 「福岡の事件を受けて、死ぬんだったらこの宗教へ行こう!助けてくれる宗教3選【天理教、キリスト教、ヴィッパサナー瞑想】」https://youtu.be/bcOYGzsjg5E 「参院 東日本大震災復興特別委員会 天理教災救隊について」https://youtu.be/wejATubiX14 「【祭典講話:安藤吉人】天理教本愛大教会 立教183年11月月次祭」https://youtu.be/TylWNp4fhgk




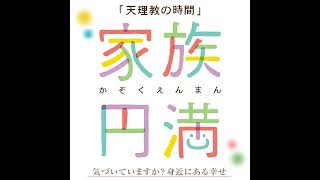

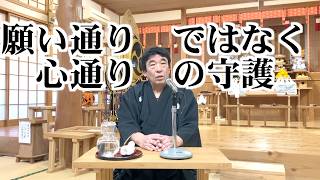
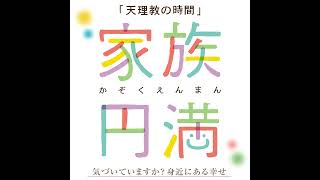


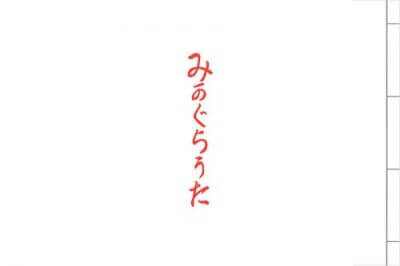
に行こう!2025年イベント情報をお届け!.jpg)
